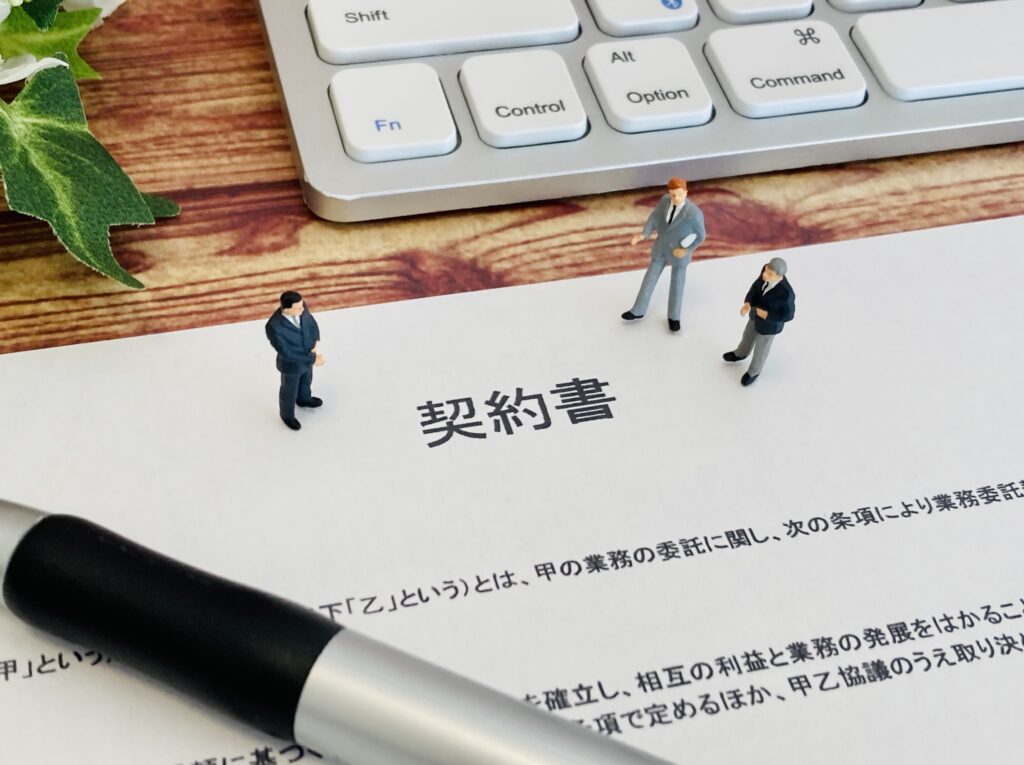営業チームの連携を強化するための施策はどのようなものでしょうか。
■ 営業チームの連携を強くする施策
1. 情報共有のルールをそろえる
メール、チャット、CRMなどの「どこに何を書くか」を明確にします。
情報が散らばると、同じ顧客に複数の担当がバラバラに連絡してしまうなどのミスが増えます。
ルールを統一するだけで「抜け漏れ」が大幅に減ります。
2. 週次ミーティングで全体像を合わせる
週1回15~20分でよいので「案件の進捗」「困りごと」「他チームへ頼みたいこと」を簡潔に共有します。
全員が同じ方向を向けるため、無駄な動きや重複対応が減ります。
3. ペア営業・同行を定期化する
若手 × ベテラン、インサイド × フィールドなど組み合わせて同行します。
スキルを学び合えるだけでなく、「この案件は自分だけで抱え込まなくていい」という安心感にもつながります。
4. 成果のチーム表彰を取り入れる
個人表彰だけだと「自分の数字だけ」を追いがちになります。
「チーム達成率」や「チームでの改善アクション」も評価対象にすると、自然と協力が増えます。
5. 部門をまたぐ連携を見える化する
受注までに営業・商品・物流など多くの部署が関わります。
「誰がどこでサポートするのか」を図式で見える化すると、連携がスムーズになります。
顧客対応の責任が明確になり、ボールの落としどころがなくなります。
6. 困ったときの相談窓口を1つつくる
マネージャー、リーダー、または専門メンバーが担当し、案件トラブルや顧客要望の相談を受けます。
相談相手が決まっていることで、不安が減り、問題解決が早くなります。
7. 成功事例を短いフォーマットで共有する
事例共有会は時間が長くなりがちなので、
例:「背景→工夫→結果→再現ポイント」の短いフォーマットに統一すると全員が活用しやすくなります。
新人でも、「どうやれば成果が出るのか」が具体的にわかります。
■ 強調すると効果的なポイント
連携は「性格の相性」ではなく「仕組みで作れる」こと。
ルール・仕組み・場づくりの3点セットで整えると定着しやすい。
連携が強いチームは例外なく案件のスピードと顧客満足が高い。