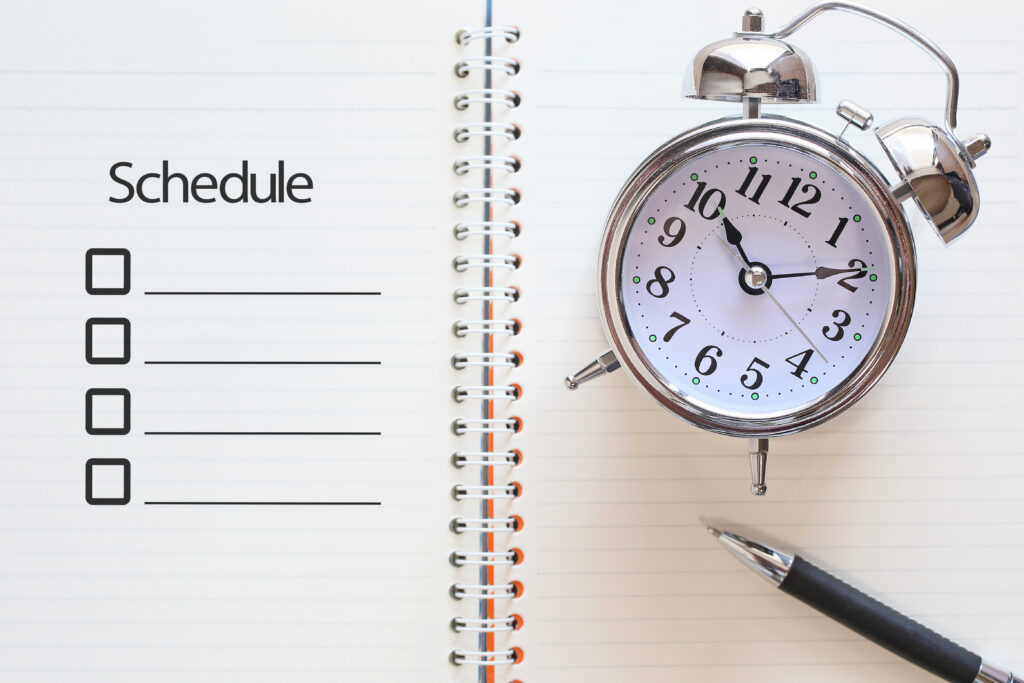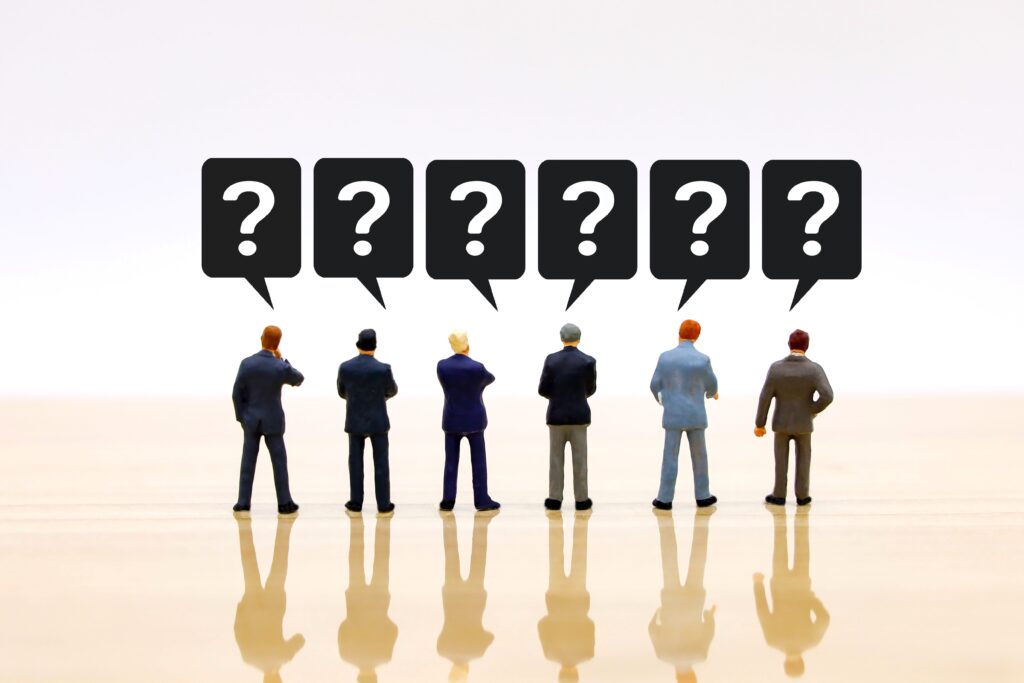営業担当者が「お客様の購買心理を正確に見抜き、適切な打ち手を選ぶため」のチェックリストをまとめました。
■ 営業向け 購買心理チェックリスト(5段階モデル対応)
【① 認知段階:知ったばかり】
お客様の状態チェック
☐ 商品・サービスの存在を知ったばかりである
☐ 課題との関連性をまだ深く理解していない
☐ 営業と会う目的があいまい
営業側の行動チェック
☐ 一方的に説明せず、状況や背景を先に確認している
☐ 「なぜこの話が自分に関係するのか」をわかりやすく伝えている
☐ 初回の印象(信頼・誠実さ・理解しようとする姿勢)を丁寧に構築している
【② 興味段階:少し気になっている】
お客様の状態チェック
☐ 商品のメリットに一定の興味を示している
☐ 質問が増えてきている
☐ 「自社でも使えるか?」のイメージを持ち始めている
営業側の行動チェック
☐ お客様の課題と商品を関連付けて説明できている
☐ お客様の言葉で語ったニーズ・困りごとを正しく復唱し整理している
☐ 興味を深めるための小さな成功例や実例を提示している
【③ 比較・検討段階:本当に良いかを見極めている】
お客様の状態チェック
☐ 他社との比較を意識している
☐ 価格・仕様・導入のハードルなど具体的な質問が出ている
☐ 社内の関係者に説明しようとし始めている
営業側の行動チェック
☐ 他社との差別化ポイントを誇張せずに明確に伝えている
☐ 導入後のイメージ(効果・手順・運用)を具体的に示している
☐ ネガティブ要素(価格・手間・リスク)も正直に説明して信頼構築ができている
【④ 確信段階:買っても大丈夫だと思えている】
お客様の状態チェック
☐ 「もし導入するとしたら…」という前向きな仮定の発言がある
☐ 導入スケジュールや社内稟議の話題が出ている
☐ 不安点が「あと数点」程度に絞られている
営業側の行動チェック
☐ 根拠(実績・データ・事例)を適切に補強している
☐ 不安点をひとつずつ丁寧に解消している
☐ 購買のリスクを下げる提案(試用、保証、段階導入など)を提示している
【⑤ 購入段階:最終決断の直前】
お客様の状態チェック
☐ 最終確認(条件・価格・契約内容)に集中している
☐ 社内の決裁者を巻き込み始めている
☐ 迷いはあるが、ほぼ前向きである
営業側の行動チェック
☐ 最終条件をシンプルに整理し、お客様が判断しやすい形で提示している
☐ クロージングが押し付けにならず、「次のステップ提案」になっている
☐ 契約後のフォロー(アフターケア・導入支援)を明確に約束している
■ 補助チェック:購買心理を動かす共通要素
信頼要素
☐ 誠実な態度
☐ 過剰な自社アピールを避けている
☐ お客様の話を遮らず最後まで聴けている
価値訴求要素
☐ 「商品説明」より「お客様の成果」に焦点を当てている
☐ 数字・事例で根拠を示している
☐ 抽象的な表現を具体化できている
不安解消要素
☐ 価格以上の価値を論理的に説明できる
☐ 導入後の失敗リスクを減らす提案が用意されている
☐ 社内説得の材料(資料・根拠)が提供できている