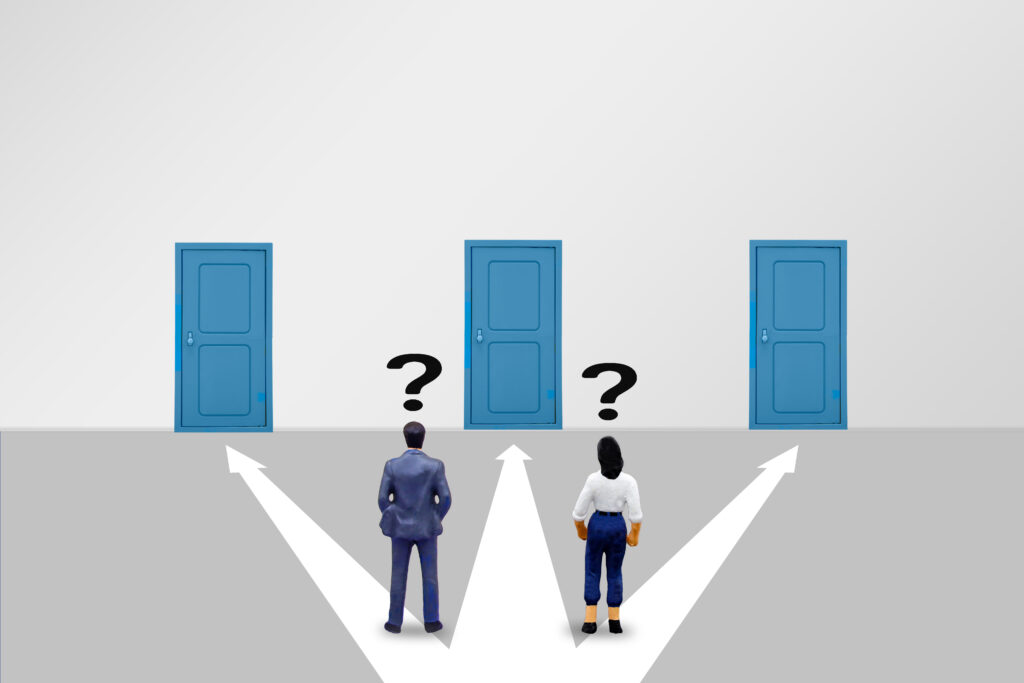第1問: あなたは大手製造業の経営層です。 現在、競争が激化している市場で自社のシェアは伸び悩んでおり、また、業界全体でデジタル化の進展が急速です。自社の製品は高品質であるものの、製造工程が手作業中心であり効率が悪いため、コストが高くなりがちです。このような状況で、デジタル化や自動化を進めるべきか、それとも既存の製品を改良して価格競争に参加するべきか、経営層としての決断を下さなければなりません。
この状況において、経営層として最も適切な対応はどれか?
A. デジタル化や自動化を進めて、長期的にコストを削減し、競争力を強化する
B. 価格競争に参加し、即効的に市場シェアを拡大する
C. 既存の製品に焦点を当て、価格を大幅に下げて市場シェアを拡大する
D. 高品質の製品に特化し、プレミアム価格で差別化を進める
正解: A. デジタル化や自動化を進めて、長期的にコストを削減し、競争力を強化する
解説:デジタル化や自動化は、長期的な視点で見た場合、コスト削減や生産性向上を実現し、最終的には市場での競争力を強化する重要な戦略です。
価格競争に参加すると、短期的には売上が増えるかもしれませんが、利益率の低下を招き、最終的にはブランド価値が損なわれるリスクがあります。
デジタル化を進めることで、効率化とコスト削減が可能となり、競争力のある価格設定が可能になります。
第2問: あなたは大手小売業の経営陣です。近年、消費者の購買行動がオンラインにシフトし、店舗型ビジネスが縮小しています。また、若年層を中心に環境意識が高まっており、サステナブルな商品や企業活動が注目されています。あなたの企業は、主に物理的な店舗販売に依存しており、オンライン販売が十分に強化されていません。この市場変化に対応するため、どのような戦略を取るべきか、経営陣として決断を下さなければなりません。この状況で、経営層として最も適切な対応はどれか?
A. 物理店舗を縮小し、オンライン販売を強化して新たな市場に対応する
B. 現状の物理店舗を維持しつつ、オンライン販売は補助的な位置づけにとどめる
C. サステナブルな商品ラインを強化し、環境意識の高い消費者層をターゲットにする
D. 新しい業態に進出し、物理店舗とオンラインの両方を拡充する
正解:A. 物理店舗を縮小し、オンライン販売を強化して新たな市場に対応する
解説:消費者の購買行動がオンラインにシフトしている中、オンライン販売の強化は今後の成長に不可欠な要素です。物理店舗が縮小する一方で、オンラインショップやeコマースの拡大は、若年層を中心に需要が急増しています。サステナビリティも今後の競争力を高める要素となり得ますが、オンラインシフトを進めることが最も効率的で長期的な成長を見込める戦略となります。
第3問
あなたはグローバル展開をしているIT企業の経営陣です。現在、国内市場は成熟期に入り、成長が鈍化しています。一方、海外市場、特にアジア地域では、急成長している国々があり、競合他社が先行しています。しかし、海外進出には法規制や文化の違い、政治的リスクが伴い、進出に慎重になるべきという意見もあります。経営陣として、海外市場への進出についてどのように決断すべきかが問われています。この状況で、経営層として最も適切な対応はどれか?
A. 海外進出を積極的に進め、アジア市場の急成長に乗り遅れないようにする
B. 海外市場への進出は慎重に行い、まずは現地のパートナーとの提携や現地法人設立から始める
C. 国内市場の強化に注力し、海外進出は現時点では見送る
D. 海外進出を完全に拒否し、国内市場における差別化を進める
正解:B. 海外市場への進出は慎重に行い、まずは現地のパートナーとの提携や現地法人設立から始める
解説:海外進出には多くのリスクが伴いますが、慎重に進めることが最も重要です。現地パートナーとの提携や現地法人設立を通じて、現地市場に対する理解を深め、リスクを軽減することが賢明です。急成長している市場に乗り遅れることなく、リスクを管理しつつ、進出を成功させるための戦略的なアプローチが求められます。
長期的な視点で企業の方向性を決定するために必要な戦略的判断を問う内容です。どれも慎重なリスクマネジメントと、将来的な成長に向けた投資判断が求められます。
 xr:d:DAFhWGi8MLE:626,j:4698421195,t:23051503
xr:d:DAFhWGi8MLE:626,j:4698421195,t:23051503